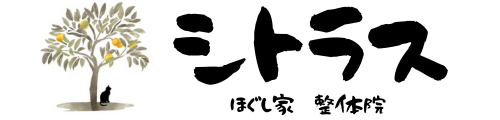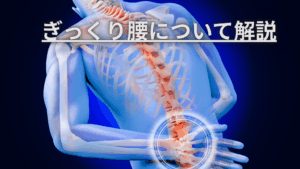フレイルについて現役理学療法士が解説
Contents
【徹底解説】フレイルとは?原因・症状・予防法を分かりやすく解説
目次
- フレイルとは何か?
- フレイルの主な原因
- フレイルの症状とサイン
- フレイルとサルコペニアの違い
- フレイルのリスクと進行した場合の影響
- フレイルの予防と改善方法
- フレイル予防のための日常生活のポイント
- まとめ

フレイルとは何か
フレイルとは、高齢期にみられる心身の衰えを指す言葉で、健康な状態と要介護状態の中間に位置する状態です。日本語では「虚弱」と訳されることもありますが、最近では医療・介護業界を中心に「フレイル」という表現が一般的になっています。
フレイルは、身体的な衰え(筋力低下、体重減少など)だけでなく、精神的・社会的な側面も含まれます。例えば、うつ状態や社会的孤立もフレイルの重要な要素です。
フレイルの定義
日本老年医学会は、以下の3つの側面を総合して「フレイル」と定義しています。
- 身体的フレイル:筋力低下、歩行速度の低下など
- 心理的・認知的フレイル:抑うつ、認知機能低下
- 社会的フレイル:独居、社会的交流の減少
フレイルは適切に対処すれば、予防や改善が可能な reversible(可逆的)な状態です。早期発見と対策が重要です。
フレイルの主な原因
フレイルの原因は複数ありますが、代表的なものは以下の通りです。
1. 加齢
加齢による自然な身体機能の低下は、フレイルの最大の要因です。特に筋肉量の減少(サルコペニア)は、身体的フレイルを引き起こします。
2. 栄養不足
偏った食生活や低栄養状態は、筋肉量の減少や免疫力の低下を招き、フレイルを進行させます。
3. 身体活動量の低下
運動不足は筋力低下の大きな要因です。特に高齢者では、日常生活での活動量の減少がフレイル進行を早めます。
4. 慢性疾患
糖尿病、心疾患、関節疾患などの慢性疾患を抱えている場合、フレイルのリスクが高まります。
5. 精神的・社会的要因
うつ病や社会的孤立もフレイルを悪化させる要因です。孤立により食事量が減少したり、外出が減ったりすることがフレイルを進行させます。
フレイルの症状とサイン
フレイルは自覚しにくいことが多いため、早期にサインを見逃さないことが重要です。以下は主な兆候です。
- 体重減少(半年で2〜3kg以上)
- 握力低下(男性26kg未満、女性18kg未満)
- 疲れやすい(軽い活動でも疲労感)
- 歩行速度の低下(1.0m/s未満)
- 身体活動量の低下(外出が週1回未満)
これらのうち3つ以上に当てはまる場合、フレイルと診断される可能性があります。
フレイルとサルコペニアの違い
「フレイル」と「サルコペニア」は混同されがちですが、異なる概念です。
| 項目 | フレイル | サルコペニア |
|---|---|---|
| 定義 | 心身の総合的な衰え | 筋肉量と筋力の低下 |
| 範囲 | 身体・心理・社会的側面を含む | 主に身体的側面 |
| 進行 | 介護リスクが高まる | フレイルの一因 |
サルコペニアは、フレイルの一部分にあたるものです。サルコペニアを予防・改善することは、フレイル予防にもつながります。
フレイルのリスクと進行した場合の影響
フレイルが進行すると、以下のリスクが高まります。
- 転倒・骨折
- 入院リスク増加
- 認知症の進行
- 要介護状態になる可能性
- 死亡リスクの上昇
特に、転倒による骨折は寝たきりにつながる大きな要因です。フレイルは生活の質(QOL)を著しく低下させるため、進行前に介入することが重要です。
フレイルの予防と改善方法
フレイルは予防と改善が可能です。以下の対策を日常に取り入れることが推奨されています。
1. バランスの良い食事
- タンパク質(肉、魚、大豆製品)をしっかり摂取する
- 栄養不足に注意し、体重減少を防ぐ
- ビタミン、ミネラルも意識的に取り入れる
2. 適度な運動
- ウォーキングやスクワットなど、筋肉を使う運動を継続する
- できれば週2〜3回、軽い筋力トレーニングを行う
- ストレッチやバランス運動も有効
3. 社会参加の維持
- 地域のサロン、趣味活動、ボランティアなどに積極的に参加する
- 家族や友人とのコミュニケーションを意識的に増やす
4. 定期的な健康チェック
- 定期的に体重、筋力、歩行速度を確認する
- フレイルチェック(自治体や医療機関で実施)を受ける
5. 心のケア
- うつ病や認知症の早期発見も重要
- 趣味や日々の楽しみを持つことが心理的フレイル予防につながる
フレイル予防のための日常生活のポイント
フレイル予防は特別なことをしなくても、日常生活を少し意識するだけで実践できます。
- 毎日10分でも歩く習慣を持つ
- 朝昼晩しっかり食事をとる
- 週1回は家族や友人と交流する
- 家事や買い物など、身体を動かす場面を増やす
- 趣味や目標を持ち、生活に張り合いを作る
こうした**「いつもの生活を丁寧に送ること」が、結果的にフレイル予防に直結します。**
まとめ
フレイルは高齢社会において非常に重要な健康課題です。フレイルは進行すると生活の質が低下し、要介護や寝たきりに直結するリスクがあります。しかし、フレイルは早期発見と適切な対策を行えば、予防・改善が可能な状態です。
バランスの良い食事、適度な運動、社会参加、心のケアなど、日常生活の工夫がフレイル予防のカギとなります。最近では、自治体によるフレイルチェックや地域包括支援センターでの取り組みも広がっています。
自身や家族の健康を守るために、「フレイル」という言葉を知り、正しい知識と予防法を実践することが、これからの時代に求められています。
アクセス・お問い合わせ
シトラスほぐし家整体院
- 住所:東京都羽村市小作台3-13-7
- 電話:090-8106-9955
- 営業時間:9:00〜17:00
- 定休日:火・日曜日
- アクセス:JR青梅線小作駅から徒歩5分/無料駐車場あり
- LINE予約:@citrus_hogushi
- 公式サイト:https://www.citrus-hogushi.jp