ロコモティブシンドロームについて理学療法士が解説
Contents
【完全ガイド】ロコモティブシンドロームとは?原因・症状・予防法を徹底解説
目次
- ロコモティブシンドロームとは?
- ロコモティブシンドロームの主な原因
- ロコモティブシンドロームの症状と診断基準
- ロコモティブシンドロームとフレイル・サルコペニアの違い
- ロコモティブシンドロームのリスクと進行後の影響
- ロコモティブシンドロームの予防と改善方法
- 日常生活でできるロコモ予防のポイント
- まとめ

ロコモティブシンドロームとは
ロコモティブシンドローム(通称:ロコモ)とは、運動器の障害によって移動機能が低下し、要介護や寝たきりになるリスクが高い状態のことです。
日本整形外科学会が提唱した概念で、ロコモは骨、関節、筋肉、神経などの運動器全体の衰えを指します。
簡単に言うと、「立つ・歩く・階段を上る」といった日常動作がしづらくなる状態がロコモティブシンドロームです。日本では高齢化に伴い、ロコモになる人が急増しており、社会問題となっています。
ロコモの現状
- 日本では、40歳以上の約4700万人がロコモ予備群と言われています。
- ロコモは40代から進行し、早期の対策が必要です。
- 要介護になる最大の原因は運動器障害であり、ロコモはその最初のサインとされています。
ロコモティブシンドロームの主な原因
ロコモティブシンドロームは、様々な運動器疾患や生活習慣が重なって発生します。
1. 加齢に伴う運動器の衰え
- 筋力低下(サルコペニア)
- 骨密度の低下(骨粗しょう症)
- 関節の可動域の減少(変形性関節症)
2. 運動不足
- 日常生活の歩行不足
- 座りっぱなしの生活習慣
3. 運動器疾患
- 変形性膝関節症
- 変形性腰椎症
- 骨折(大腿骨頸部骨折など)
- 脊柱管狭窄症
4. 体重増加
- 肥満は膝や腰に過剰な負担をかけ、関節疾患のリスクを高めます。
5. 栄養不足
- タンパク質、カルシウム、ビタミンDの不足は筋力・骨密度低下を引き起こします。
ロコモティブシンドロームの症状と診断基準
ロコモは自覚症状が少ないまま進行することが多いため、セルフチェックが重要です。
主な症状
- 階段を上るのがつらい
- 片脚立ちがふらつく
- 歩くスピードが遅くなる
- 転びやすくなる
- 足腰の痛みや違和感がある
- 長時間歩けない
ロコモチェック(7項目)
日本整形外科学会が推奨するセルフチェック項目は以下の通りです。
- 片脚立ちで靴下がはけない
- 家の中でつまずいたり滑ったりする
- 階段を上るのに手すりが必要
- 家のやや重い仕事が困難
- 2kg程度の買い物袋を持ち帰るのが難しい
- 15分くらい続けて歩けない
- 横断歩道を青信号で渡り切れない
1つでも当てはまる場合は、ロコモの可能性があります。
ロコモティブシンドロームとフレイル・サルコペニアの違い
ロコモ、フレイル、サルコペニアは似たような概念ですが、それぞれの定義と対象が異なります。
| 用語 | 意味 | 主な対象 |
|---|---|---|
| ロコモティブシンドローム | 運動器の障害による移動機能低下 | 骨、関節、筋肉、神経 |
| フレイル | 心身の総合的な虚弱状態 | 身体・精神・社会的側面 |
| サルコペニア | 加齢による筋肉量・筋力の低下 | 筋肉・筋力 |
まとめると
- ロコモ:運動器全体の問題
- サルコペニア:筋肉の問題
- フレイル:生活機能全体の衰え
ロコモが進行すると、サルコペニアやフレイルを合併することが多く、相互に影響し合います。
ロコモティブシンドロームのリスクと進行後の影響
ロコモを放置すると、以下の深刻なリスクにつながります。
- 転倒・骨折リスクの増加
- 外出機会の減少(社会的孤立)
- 要介護状態への進行
- 寝たきり・認知症リスクの増加
- QOL(生活の質)の著しい低下
転倒 → 骨折 → 入院 → 寝たきりという負のスパイラルに陥ることが、ロコモの最大の問題です。
早期対策が重要
ロコモは進行する前に予防・改善することで、要介護や寝たきりを防ぐことができます。
ロコモティブシンドロームの予防と改善方法
ロコモ対策は運動・栄養・生活習慣の3本柱が重要です。
1. ロコトレ(ロコモ予防運動)
日本整形外科学会が推奨するロコトレ(ロコモティブトレーニング)を日常生活に取り入れましょう。
● 片脚立ち
- 片脚で1分間立つ(左右各1分、1日3回)
- 転倒しないように支えのある場所で実施
● スクワット
- ひざを曲げすぎず浅めにゆっくり10回×3セット
- 太もも、膝、腰を鍛える基本運動
2. 日常生活での活動量を増やす
- エレベーターではなく階段を使う
- できるだけ歩いて買い物に行く
- 家事を積極的に行う
3. バランスの良い食事
- タンパク質(肉、魚、大豆製品)を毎食しっかり摂取
- カルシウム・ビタミンD・ビタミンKを意識する
- 適度な体重管理で関節への負担を軽減
4. 定期的な運動習慣
- ウォーキング、ストレッチ、筋トレを継続的に行う
- 週に150分以上の中強度の有酸素運動が理想
5. 定期検診と早期治療
- 骨密度検査、関節の定期チェック
- 膝や腰の痛みがあれば早めに医療機関を受診
日常生活でできるロコモ予防のポイント
- 歩く機会を意識的に増やす
- エスカレーターより階段を選ぶ
- 買い物や家事で身体を動かす
- 無理なく続けられる運動を習慣化する
- 食事は1日3食しっかり摂り、タンパク質を多めに摂取する
- 外出や社会参加を積極的に行う
ロコモは毎日の小さな心がけが大きな予防効果を生みます。
まとめ
ロコモティブシンドローム(ロコモ)は、高齢社会における重要な健康課題の一つです。
ロコモを放置すると、要介護や寝たきりに直結するリスクがあります。しかし、ロコモは早期に気付き、運動や生活習慣の見直しを行うことで予防・改善が可能です。
特に、日々の生活で「よく歩く」「バランスよく食べる」「筋力を維持する」ことがロコモ予防の基本です。家族や地域で声をかけ合い、ロコモ対策を意識することが、健康寿命を延ばす大きな第一歩になります。
ロコモチェックは、自宅でも簡単にできるので、気になる方は早めにセルフチェックや専門機関での検査を受けることをおすすめします。
アクセス・お問い合わせ
シトラスほぐし家整体院
- 住所:東京都羽村市小作台3-13-7
- 電話:090-8106-9955
- 営業時間:9:00〜17:00
- 定休日:火・日曜日
- アクセス:JR青梅線小作駅から徒歩5分/無料駐車場あり
- LINE予約:@citrus_hogushi
- 公式サイト:https://www.citrus-hogushi.jp
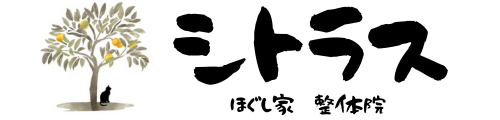


“ロコモティブシンドロームについて理学療法士が解説 ” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。